2025.11.11
【保存版】会社の忘年会を成功させる5つのステップ|幹事の負担を減らす運営術
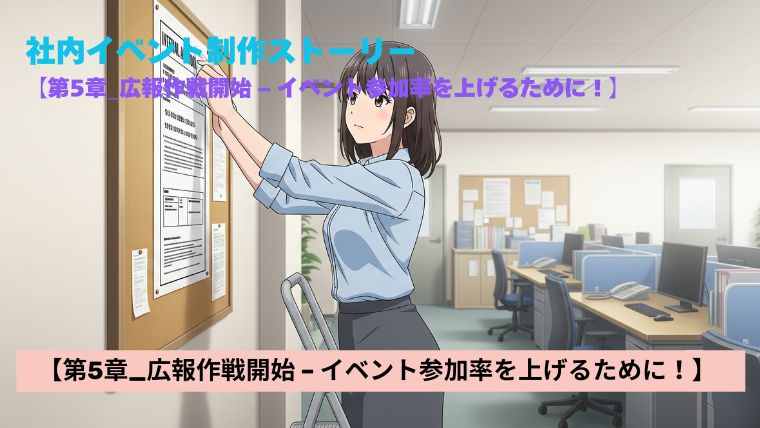
プログラムもスタッフもほぼ固まり、「あとは当日を迎えるだけ!」—そう言い切れたらどんなに楽だっただろう。
しかし、まだ最大の壁が残っていた。それは、参加者集めだ。
社内イベントは、どれだけ企画が良くても、人が集まらなければ成立しない。
むしろ、参加率の低さはそのまま企画担当者の評価に直結する。
頭ではわかっていたが、現実として「集客」という言葉の重さが、ずしりと肩にのしかかる。
私は「これなら楽しんでもらえる!」という自信を持っていた。
でも、そのワクワクをどうやって社内全員に伝えるか?
一歩間違えば「また総務がやってる恒例行事」程度に受け止められてしまう。
新鮮味がなければ、人は動かない。
まずは社内SNSに告知を投稿した。イベントの概要、日時、場所、プログラムの一部をシンプルに書き、申し込みフォームのリンクもつけた。
投稿直後、「いいね」が数件ついたが、肝心の申込フォームはほとんど動かない。
「おかしいな…面白そうなのに」
パソコン画面を前にしてため息をつく私に、隣の席の同期・美咲が言った。
「ただの案内文じゃ、イベントの温度感は伝わらないよ。もっと、読むだけでワクワクする感じを出さないと。」
その夜、私はGROWSの島田さんに電話した。
「告知は出したんですが、申し込みが全然伸びなくて…」
電話口の島田さんは少し笑いながら言った。
「広報もイベントの一部だと思って作り込みましょう。人を動かすのは情報じゃなくて感情です。」
翌日、島田さんから送られてきたのは、GROWSが手掛けた社内イベントの広報事例集。
そこには、ただ日程や内容を並べるのではなく、写真、キャッチコピー、参加者インタビューを使った「感情に響く告知」がずらりと並んでいた。
「“行ってみたい”と思わせるのは、頭じゃなくて心に刺さる表現です。」
その言葉が胸に残った。
私は告知を一から作り直すことにした。
まず社内SNS用のビジュアルを作成。部署対抗ゲームの様子をイメージしたイラストや、昨年のイベント写真を使い、「笑顔でつながる時間 – 部署も世代も越えて楽しもう!」という大きなタイトルを配置。
さらに「参加者には豪華景品!」「当日のサプライズ演出も!」という短いキャッチを添えた。
次にポスターも制作。印刷したポスターはエントランス、食堂、エレベーター前など、人の流れが集中する場所に貼った。QRコードを添え、スマホからその場で申し込めるようにした。
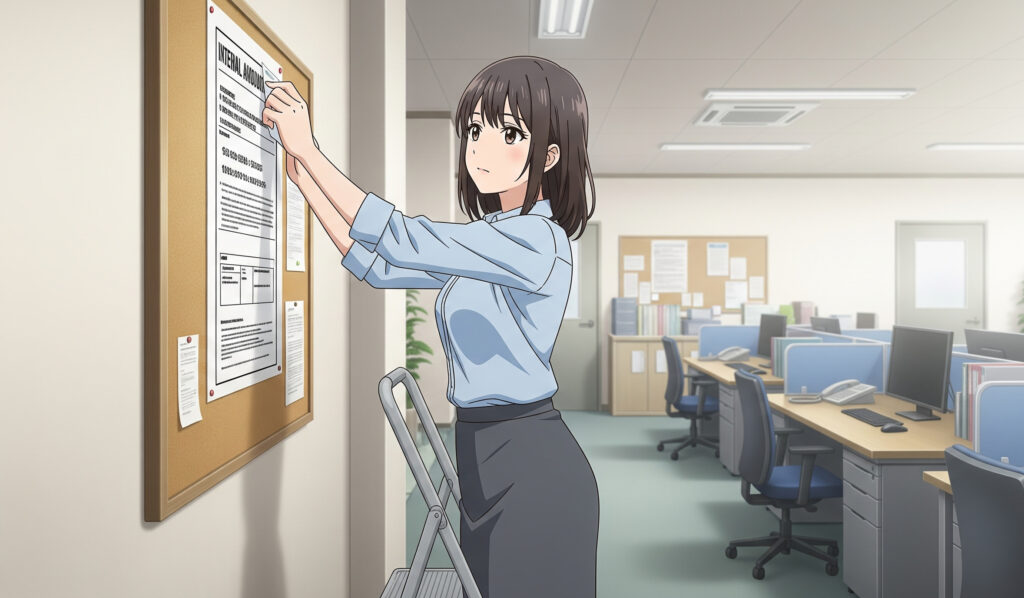
しかし、それでも申込数はじわじわとしか増えない。
焦る私に、島田さんがもう一つアドバイスをくれた。
「告知は“全体告知”と“ピンポイント告知”を組み合わせましょう。特に部署単位や個人への直接アプローチは効果的です。」
私はすぐにスタッフを招集し、各部署の昼休みに5分間だけのミニ説明会を行うことを提案。
スタッフが日替わりで出向き、「部署対抗戦で優勝したら景品が!」「普段話さない人と交流できるチャンスです!」と笑顔で伝えると、その場で申し込みをしてくれる人が増えていった。
さらに私は、去年参加したベテラン社員に「昨年の感想」を社内SNSに投稿してもらうようお願いした。
「普段話せない人と知り合えた」「他部署との距離が縮まった」——こうしたリアルな声は、私が書く案内文よりもはるかに説得力があった。
それが口コミのように広がり、「じゃあ自分も行ってみようかな」という人が増えていった。
開催1週間前、ついに目標人数を突破。
スタッフ全員でハイタッチを交わしたとき、胸の奥がじんわり温かくなった。
数字だけでなく、社内全体がイベントに向けて盛り上がっているのを肌で感じたからだ。
その夜、家で天井を見上げながら思った。
——イベントは、当日だけで作られるものじゃない。
準備段階からすでに、私たちは参加者と一緒に物語を作っているんだ、と。
そして、私の頭には次の課題が浮かんでいた。
「さて、当日の“見せ場”をどう盛り上げるか——」
その瞬間、心の奥で静かにスイッチが入る音がした。
次章、「いよいよ本番直前準備」へ!
