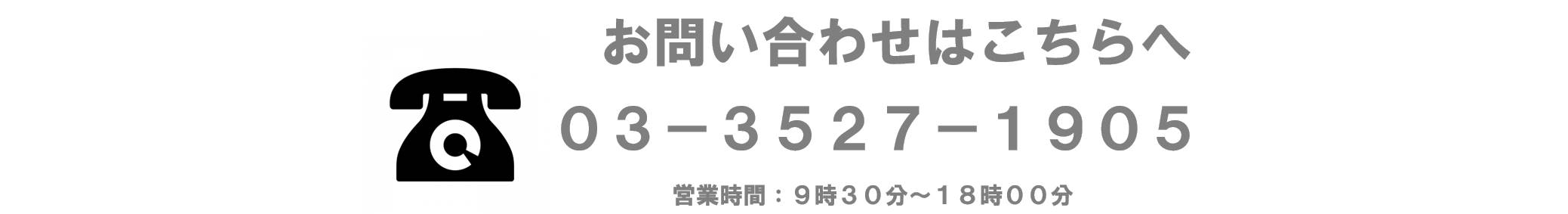2025.04.18
東京ビッグサイトで社内表彰式を開催するには?会場選び・演出・運営のポイントを徹底解説!

いきなりですが、社内イベントに「行きたくない」「参加したくない」と思ったことはありますか?僕らは社内イベントの企画を行っている会社なので、このキーワードはとても恐ろしいです。
ただ、検索トップに「社内イベント 行きたくない」が来ます。それくらい検索している人が多い言うことでしょう。
この事実に対しては、真摯に向き合うしかないと思います。その事実を踏まえたうえで、僕ら企画会社は良い企画、価値のある企画を考えるべきであると、それら課題を解決するために存在すると改めて介在の価値を感じました。
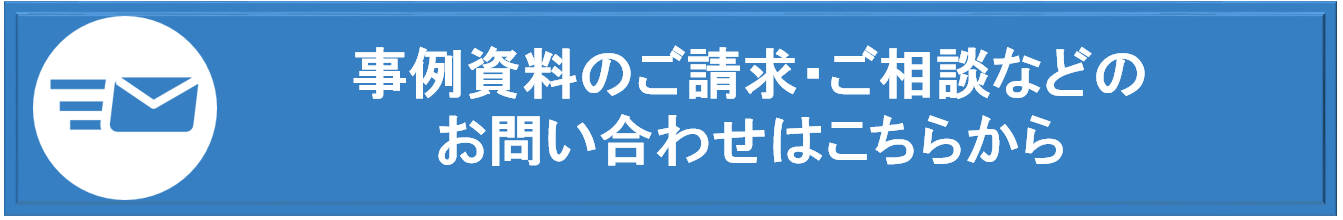

様々な理由が考えられます。ある企業で調査した結果では、以下のような項目が挙げられました。
・わざわざ全員で集まる必要がない。一部の人だけが盛り上がっている
・会社のことと、自分のことを別に感じる
・社長のスピーチが長い。現場に即してない感じがする
・通常業務が忙しくて、それどころではない
・単純につまらない
・自由参加といいながら、半強制参加
・この会社に長く務める予定がない
などなど。挙げていくとたくさんのご意見が出てきました。
社内イベントとひとくくりに行っても様々なものがあります。例えば、部署単位の飲み会、懇親会から始まり、全社員が集まるような大型企画までいろいろな形があります。
特に、大型企画になればなるほど、自分とは遠い存在に見えてしまい参加意識は下がる傾向があります。逆に小規模企画の場合は、飲まされるのが嫌、上司に気を遣うのが嫌など自分を中心としたネガティブな気持ちが多くなります。
それらを踏まえて、社内イベントにはネガティブなマインドはある。という前提に立つことが企画担当者が意識しないといけないことかもしれません。企画する側の視点と、参加する側の視点、この両方の視点をバランスよく持つことが企画を遂行するにあたっては外すことはできないポイントです。
その他、社内イベントに参加したくない理由として、以下が挙げられます。
近年は仕事のつながりよりもプライベートを充実させたいという社員も多数存在します。休日や業務終了後に開催するイベントの場合、プライベートを優先したいからと断る社員もいるでしょう。
社内イベントを開催するとはいえ、休日を使うのであれば任意参加にするのがおすすめです。社員のなかには、社内イベントの時間を自分の趣味や家族と過ごす時間に充てたいと考える人もいます。
また「休みの日まで職場の人とコミュニケーションをとりたくない」と感じる人がいるのも事実です。とくに仕事とプライベートを完全に分けて考えたい方は、この傾向が強いといえるでしょう。
そもそも社内イベントの内容に魅力がなければ、参加しようとは思いません。例えばフットサル大会を開く場合、運動が苦手・嫌いな方が参加しようと思うでしょうか?気まぐれで「挑戦してみようかな」と思う方もでてくるかもしれませんが、大体は参加したくないでしょう。
魅力のない社内イベントは興味や関心がわかず、参加する時間がもったいないと感じてしまうものです。参加側に明確なメリットがなければ、参加率を上げるのは難しいでしょう。
社内イベントで発生する事前準備が大変なため、参加したくないと感じる人もいます。例えば、花見なら場所取りや料理のケータリングの予約が必要ですし、バーベキューなら道具のレンタルや食材の調達といった準備があります。基本的に社内イベントでは、何かしらの準備が必要です。そのため幹事を任された社員は「業務と関係ない仕事を押しつけられた」と感じてしまうのです。
また、準備を強制されると、当人のモチベーションが下がってしまいます。立候補形式で行うならまだしも、一方的に幹事役を押しつけられると苦痛に感じる人もいるでしょう。一人あたりの負担が大きく、通常業務と並行して準備を進めるのが難しい点も社内イベントが嫌われる理由です。
社内イベントの参加費が自己負担だと、社員にとって経済的な負担となってしまいます。一般的に若手社員は給料が低いケースが多いため、自己負担での参加が難しいこともあるでしょう。小さなお子様や両親といった扶養する家族がいる家庭だと、イベントの参加費用を捻出できない可能性もあります。
このように各社員で抱えている経済事情は異なります。開催側が「たった数千円」と思っていても、特定の社員にとっては大きな金額かもしれないのです。
また、金銭的負担と参加するメリットが見合わない場合も参加したくないと感じる理由のひとつです。数千円の参加費を払っておいて上司のお酌をするだけなら、大半の人は参加したくないでしょう。
会社という組織には、大々的に強制参加としていなくとも、参加しないといけない雰囲気があります。いわゆる「付き合い」と呼ばれるものです。これは社内イベントに限った話ではありません。上司からの飲み会やゴルフの誘い、取引先との食事会など、業務時間外であっても半強制的に参加しなければならないシーンは多数あります。
社内イベントに参加しないことで、周囲から「付き合いの悪いやつ」「普通は参加するでしょ…」など酷評される可能性があります。そのため、望まない社内イベントでも社員は参加せざるを得ないのです。
また、休日返上で行うイベントが普段の業務と代わり映えしないと、参加したくないと感じる人は多いです。上司や経営層が参加するイベントの場合、プレッシャーを感じて、より参加をためらう人が多くなるでしょう。
「休日返上がよくないなら社内イベントを業務時間内でやれば問題ないのか」といわれると、そういうわけでもありません。業務時間内でイベントが行われる場合、通常業務に支障をきたすおそれがあります。部署やチームによっては締め切りや納期が短いプロジェクトを抱えていることもあるため「イベントなんてやってる場合じゃない!」と思う社員もでてくるかもしれません。
とくにバーベキューや花見といったイベントでは、隙間時間に業務をこなす行為も困難です。参加だけではなく準備にも時間を割く必要があるため、かえって仕事の負担が増えてしまいます。
イベントの内容が特定の社員に偏っていると、一部の社員しか楽しめません。前述したフットサル大会は、まさにその典型といえるでしょう。スポーツ系のイベントは、社員の年齢や性別にかかわらず楽しめるイベントではありません。
多様性を尊重する現代社会において、偏ったイベントの実施は不適切といえます。社員全員の趣味嗜好に合わせるのも難しいですが、ある程度万人受けする内容にしておくべきでしょう。
お酒を伴うイベントの場合、ハラスメント行為が発生するリスクがあります。会社のバーベキューや花見といったお酒の席であっても、あくまで上司と部下の関係であることに変わりありません。
また、お酒の勢いで不適切な言動や行動にいたる方も出てくるかもしれません。飲酒の強要や飲めない人への配慮が欠けていると、参加をためらう人がいるものです。とくに女性社員や新入社員はお酒の席でも絡まれやすい傾向にあるため、ハラスメントが心配で参加したくないと思うでしょう。

参加したくない社内イベントのランキングをご紹介します。どの企画にも目的があり、価値があります。それを前提にし、どの企画が人気がないのかは知っておきましょう。
逆に言うと、人気のない企画の価値が上がれば一気に士気を高めたり、感動を伝えたりことができることも事実です。ピンチはチャンスとも捉えられますね。
社員旅行を敬遠される方が最も多くいます。上司や同僚とずっと一緒にいるのが息苦しい、常に気を遣う。などが理由に挙げられます。24時間気の抜けない時間を過ごすことにネガティブな感情を抱くケースが多いようです。
打開策としては、
・チーム分けや班分けに意味を持たせる
・ただ旅行に行くのではなく、チームビルディングや研修の要素を一部盛り込み皆で楽しめる企画を考える
・アッと驚くサプライズを用意する
・飲み会はほどほどにする
ネガティブな意見が多い企画であるため、普通の社員旅行では楽しさを伝えるのは難しいでしょう。せっかくやるなら!の気持ちで企画を織り込んでみてはいかがでしょうか。
謎解きゲームやBBQもクイズを織り交ぜたりするだけで評判は変わります。
次に敬遠されるのが、スポーツ系のイベントです。スポーツ系イベントは一見皆で参加し楽しめる企画に見えがちです。部署対抗の運動会、駅伝大会などが一般的かもしれません。
やはり、体を動かすことは苦手な人もいます。得意不得意がはっきり出ますので苦手な人も多いようです。ケガのリスクもありますので、無理のない設計が必要です。
運動会ではなく文化祭を開いた企業様もありました。運動会に寄りがちな企画を、敢えての文化祭寄りに仕立て各部署での出し物やブースで事業内容を紹介したり、取り組みを理解してもらう企画に仕立てた企業様もありました。是非、参考にしてください。
次にランクインは、野外系の飲食イベントです。特に新入社員や若手から苦手とされるケースが多いようです。どうしても野外系の企画ですと、パシリにされがちです。それ一番敬遠する理由です。
飲みすぎてしまい絡まれるのも野外イベントのあるあるといえます。こういった野外系のイベントを行う場合は、イベント会社などに相談することをご提案します。
準備からごみの片付けまで考えると全員が楽しむことは難しい状況になります。ここは割り切ってアウトソースするという考え方もありかと思います。企画を盛り込んだり、皆で参加できる企画にすることも念頭に入れてみてはいかがでしょうか。
飲み会の人気も低いです。特に酒離れが進んでいますので飲み会は苦痛の方も多いようです。新年会、忘年会、歓迎会、懇親会など様々な理由で、様々な単位で飲み会は日々開催されています。
最近は新型コロナウイルスの影響もあり、飲み会は減っていると思いますが、それでもオンライン飲み会などの言葉ができるくらい頻発しているものでもあります。敬遠される理由は、上司に絡まれる、気を遣う、飲めない、断ると付き合いが悪いと言われる。などです。部署単位など身近な単位で介されることが多い為、とても目立ちます。
逆に大型の全社を挙げての懇親会などは好評なことが多いようです。いつも食べることのできないホテルの食事が食べれる。企画があるので参加していて楽しい。などいつもの居酒屋ではなく、非日常空間を演出することは参加意識を高め、特別感を感じてもらえる仕掛けになります。
是非検討してみるのはいかがでしょうか?
最後は全社会議です。企業によって呼び名はいろいろあると思いますが、社長のスピーチやメッセージ、全社表彰式などの企画が行われます。
これらの企画が敬遠されがちな理由の一番は、自分ゴト化されないことです。全社員分の1として自分を見てしまい、他人ゴトになってしまいます。この他人ゴトになってしまう気持ちを理解しながら、自分ゴトとして捉えていただけるように企画することが担当者の腕の見せ所です。
映像による没入感を演出したり、場内をコンセプトに合わせた装飾をしたり、サプライズ企画を用意したりと、皆がその時間を共有することで、得られる価値をより多く盛り込むことや、あなたにメッセージしている。という強い思いを企画側から設計することが大事です。
最近は、オンラインでイベントを行う企業も増えてきました。オンラインという武器は、私たちに様々な効果をもたらしており、とても大きなメリットを享受しています。
関連記事
アフターコロナの社内イベントはハイブリッド化する。新しい形の社内イベントを構築するチャンスです。

ここからは、社内イベントを実施するメリットについて解説します。社内イベントが苦手な社員の多くは、「やり方」や「組織文化」に問題を感じているものです。つまり、社内イベントそのものが悪いわけではありません。本来、社内イベントには以下の効果が期待できます。
社内イベントを実施すると、社員同士のコミュニケーションが活発になり、普段話さない人とも交流が図れます。参加に意欲的でなくても、コミュニケーションの場で新しいつながりや知見を得られる機会も多いでしょう。
とくに部署間で開催するものだと、業務連絡でしかやりとりしない他部署の社員たちと、情報共有や意見交換ができます。また、社内イベントという仕事中とは異なる雰囲気によって、いつもと異なる一面を見られる点もメリットです。社員同士のコミュニケーションが活発化すると、早期離職やコミュニケーション不足によるミスを防止できます。
イベントでは各社員が持つ価値観や目標を共有できるため、組織に一体感が生まれます。
職場の一体感は業務を通じて形成されるものですが、普段とは異なる空間で打ち解け合えば、業務上では発見できなかった側面も見えてきます。ビジネス的な面だけでなく、性格や趣味嗜好といったより深いレベルでつながりを形成できるため、一体感の強い組織になるのです。
日常業務とは異なる環境に身を置くことで、心身のリフレッシュや、モチベーションアップにもつながります。開催方法が適切でない社内イベントだと、かえって不満や疲労を招いてしまいますが、配慮と工夫1つでそれらの問題は解決できます。
例えば「上司へ一方的に気を遣い続けるのが苦痛」といった方が多いなら、同じ役職・性別といったカテゴリで席配置を行う方法がおすすめです。席配置がランダムだと、新入社員が重役に挟まれる可能性もゼロではありません。できるだけイベントを楽しんでもらうためにも、席配置に気を配るとよいでしょう。
また、普段かかわらない社員とコミュニケーションを取ることで、自分の業務の意義を再確認できます。自分の業務が企業にとってどのようにプラスになっているか、社内の立ち位置を知るいいきっかけにできるでしょう。このように、他部署の社員とコミュニケーションを取ることは、モチベーションアップにつながります。

企業は何故社内イベントを行うか?この疑問を考えます。
参加したくないと思う人もいますが、参加したいと思う人も多くいます。まずは、求めている人もいるということが前提であり、求めてほしいと思いながら企画することが大切であると考えます。
仕事を進めるうえで、情報のやり取り、ツールの共有、タスクの進捗に関してはオンライン化が進み効率化され生産性も向上しました。ただ、コミュニケーションという観点では、失ったものもあります。円滑なコミュニケーションは業務生産性を大きく向上させます。そして、良好なコミュニケーションは社員の離職を防ぐことに役立ちます。
嫌がるイベントを強制することはできませんが、全員が同じ方向を向くきっかけを作ることは組織運営において必要なことです。大切なメッセージをインパクトの残る形で伝える。忘れてしまいそうなタイミングでリマインドする。手元のツールや社内メルマガなどでリマインドをしていく。この繰り返しこそが強い組織づくりの最短距離です。
もちろん社内イベントですべてを解決できるものではないので、それらを取り巻く全ての企画を包括的に設計していくことが大切になってきます。

ここからは、社員が「参加したい」と思ってくれるような、社内イベントにするコツを解説します。社内イベントの参加率を向上させたい方は、以下の点を意識しましょう。
社内イベントの実施や企画は、事前に社内で共有しましょう。どんなイベント内容にすべきか不透明さが目立つなら、アンケートを実施するのも効果的です。社員のニーズや気持ちを把握することで、参加率や満足度の大幅な向上が見込めます。
またイベント内容が決定した際に、概要や開催目的といった詳細な情報を共有すれば、そのイベントにどのようなメリットがあるかを社員が判断できます。共有は漏れがでないよう、掲示板や社内のチャットツールなど、さまざまな媒体で行いましょう。
1度だけの告知では見逃してしまう社員がいる可能性があるため、情報の共有は繰り返し行う必要があります。チャットや掲示板も効果的ですが、大人数・関連企業も参加するなど規模が大きい場合は、社内報やチラシなども利用しましょう。
また、定期的なリマインドは、参加者のモチベーション維持にもつながります。当初は参加に意欲的でも、時間が経つにつれて気持ちが薄れてしまうかもしれません。詳細な日程やイベントの存在を忘れてしまう可能性もゼロではないため、参加率を上げるにはリマインドが必須です。
休日はプライベートの時間を優先したいと考える社員がいるため、平日開催にするのも参加率をアップさせる手段のひとつです。業務時間内に収まるイベントであれば、より参加率があがるでしょう。休日開催は、事実上会社の都合に社員が合わせている状態です。
社内イベントは、基本的に会社側がなんらかの目的を持って開催するものです。会社側から提案する以上、本来なら譲歩する側は会社でなければなりません。イベントを実施する際は社員に余計な負担をかけないために、配慮するとよいでしょう。
平日開催の場合、業務時間を1日あるいは半日程度費やします。開催にあたっては、繁忙期に入っている部署やチームがないか、事前にスケジュールを調整しておきましょう。社員にとって負担にならない日程を選定することが大切です。
社内イベントを告知する段階で、イベント参加によりどのような恩恵が受けられるかを伝えましょう。イベント内容を「楽しそう」と思ってもらうことも大切ですが、具体的なメリットがないと参加率は下がってしまいます。
例えば、ビンゴゲームなら入賞者に対して送られる豪華賞品です。場合によっては、景品を特別休暇にしてもよいでしょう。イベント参加のメリットは必ずしも景品や報酬である必要はありませんが、わかりやすいメリットがあると参加率は大きく上がります。
多種多様な社員がみな楽しめるイベントを企画し、イベントの目的や背景なども伝えるとより効果的です。
社内イベントは、総じて準備に手間がかかります。飲み会ならお店やケータリングサービスの予約が必要ですし、ビンゴゲームなら景品を用意しなければなりません。とくに参加人数の多いイベントだと、幹事役を務める社員の負担は大きくなります。社内イベントを実施する際は、できるだけ準備の少ない、もしくは不要な内容にするとよいでしょう。
どうしても準備に手間がかかる場合は、幹事の人数を増やして、負担を分散させます。また、幹事役に報酬を与えることで、任せられた側も「やり損」と感じにくくなります。
繁忙期で時間が取れないなら、イベント代行会社に委託する方法もおすすめです。

コミュニケーションの活発化や組織力の向上を目的とするなら、社内イベントだけにこだわる必要はありません。例えば、社内SNSの活用やボランティア活動の推奨は、社内イベントの代わりになり得ます。
また、社内表彰制度を充実させれば、社員のモチベーションアップにつながるでしょう。オフィス内にカフェスペースやリフレッシュスペースを設けるのも1つの手段です。このように社内イベントの代替案は複数存在するため、社内の課題を解決できる最適な方法を選択しましょう。

ここからは、社内イベントの主催側ではなく、参加する側の心がけについて解説します。社内イベントは、本来楽しいものでなければなりません。社内イベントに対してマイナスイメージを抱く方も珍しくありませんが、気持ちの持ち方1つで楽しめるかどうかは変わるものです。
自分なりの目的を持つと、参加するモチベーションがあがります。例えば、おいしいものを食べる、普段話したことがない人と会話をしてみるなど、1つでもよいので目的を持ってイベントに参加するとよいでしょう。
別部署の社員と交流することで業務上での連携がスムーズにいく可能性もあります。今後の業務によい影響があるなら、イベントに参加する価値は十分あるといえるでしょう。
職場の人に対して興味を持ち、さまざまな情報を得ようとする意識をもちましょう。社内イベントは、普段の業務中では話さないようなことを聞ける絶好の機会です。
話そうという意識を持つだけでも、コミュニケーションの活性化につながります。イベントでコミュニケーションを図ると、業務時のトラブルでもお互い声をかけやすくなるでしょう。
社内イベントはつまらないという固定観念を捨てることも大切です。消極的な目線だと見えるものも見えなくなるため、非常にもったいないです。
「社内イベントでコミュニケーションを取ると業務に役立つ」と考えることで、これまで見えてこなかった知見を得られます。新しい知識や考えはこれからの業務にも活かせるため、業務のマンネリ化を感じている社員のモチベーションアップにつながるでしょう。
社内イベントをもっと良くしたい。もっともっと成長の機会にしたい。
マンネリ化してしまっているなどの、ご相談は是非GROWSまで。
よろしくお願いします。